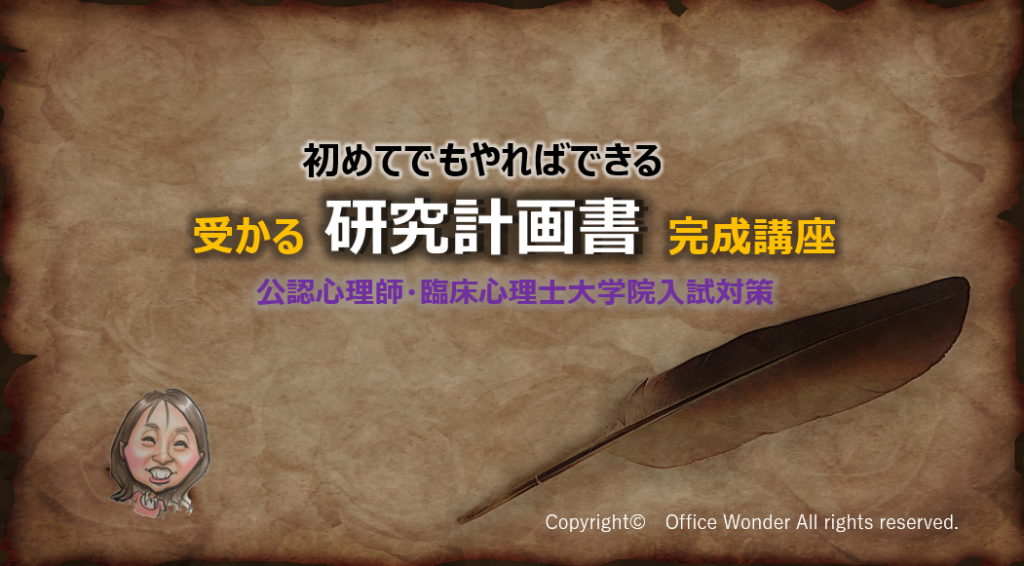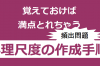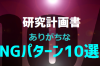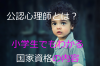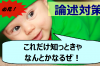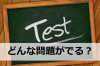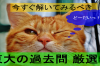ご訪問ありがとうございます。こんにゃろうです。
受験すると決めたら、なるべく早く過去問をチェックしよう。
今回は、心理系大学院の筆記試験についてです。
まず、確認しておきたいのが、心理系大学院の入試の3つの合否の判断基準です。
です。
筆記試験はこの中でも、最も重要だと考えられます。
何故なら、大学院は研究するところ。研究するにあたって、基本的な知識があるのか?英語力があるのか?論文を書く力があるのか?というところを、見られるからです。それを判断するのが筆記試験。口述試験でどれだけよい印象を与えられたとしても、基礎学力がないと判断されてしまったら……合格は難しいと思います。
ということで、今回は、筆記試験は、一体どんな問題が出るの??というところを、いくつかの過去問の例をあげながら、考えていきたいと思います。。これから受験対策を始めようとするあなたに、だいたいこんな感じなんだな、とつかんでもらえると嬉しいです。
筆記試験は「専門科目」と「英語」の2つです。両方について書くと量が膨大になってしまうため、「英語」は別の機会に書くとし、今回は「専門科目」のみを取り上げます。
(英語についてはこちら⇒最強の英語対策!合格するために必須の4つの力|臨床心理士指定大学院入試対策)
専門科目
専門科目というのは「心理学」のことです。「心理学」は主に、「基礎心理学」と「臨床心理学」にわけられます。臨床心理士や公認心理師の資格を取るためには。大学院は、臨床心理学を専攻することになるので、【臨床心理学】に関する問題が中心に出されます。その他に【基礎心理学】の基本的知識に関する問題が出されます。大学院によってその傾向はそれぞれ違いますが、とりあえずは、オーソドックスな例を紹介しています。
心理学用語の用語説明 1試験で5題~10題 (1題につき200字程度を求められる場合が多いが、罫線のみ引いてあって文字数の指定のない場合もある。)
例:次の用語の心理臨床上の意味を簡潔に説明しなさい。
予期不安 / シゾイドパーソナリティー / 置き換え(防衛機制) / 身体化 / 複雑性トラウマ / ポスト・フェストゥム / 病態水準(カーンバーグ) (学習院大学大学院2025年度 )
例:以下の用語について簡潔に説明しなさい。(100字程度)
教育機会確保法 / ロゴセラピー/ 結晶性知能 (大正大学大学院 2025年度)
※専門的な知識を正確に書くことが求められる。「◎◎とは●●である。」という専門的な定義を書き、代表的な提唱者、実験内容など、を書いていく。また正確な日本語力も必要。(詳しくはこちら⇒用語説明問題でやってはいけない8つの事【絶対保存版】|臨床心理士指定大学院受験)
論述問題 1試験で2題~3題 (1題につき400字~1000字)
例:子供に知能検査を実施する際の留意点について述べなさい(600字以内)。(放送大学大学院 2012年度)⇒この問題についての解説をこちらに載せています⇒知能検査を行う際の留意点とは?【放送大学大学院過去問】臨床心理士指定大学院入試対策
例:精神分析と行動療法の理論においては,セラビストークライエント関係について どのような違いがあるか。
(立命館大学大学院 2020年度)
例:仲間はずれやいじめ、虐待などの社会的排除(social exclusion)を受けた人の一次的・二次的障害を指摘した上で、周囲がその障害に対してどのような支援をする必要があると考えられるか、見解を述べなさい。(専修大学大学院 2022年度)
例:近年、臨床心理学が専門活動として発展するにしたがって、倫理の重要性が強調されるようになっている。臨床心理学において倫理が重要である理由について述べなさい。 (東京大学大学院 2011年)⇒この問題についての解説をこちらに載せています⇒今すぐ解いてみるべき!おすすめ東大の過去問【厳選5選】|臨床心理士指定大学院対策
例:心理尺度作成の方法と手順について、1000字以内で具体的に説明しなさい。(横浜国立大学大学院 2012年度)⇒この問題についての解説をこちらに載せています⇒心理尺度の作成手順|覚えておけば満点がとれる頻出問題|臨床心理士指定大学院対策
例:小学3年生の女児が学習不振を主訴に母親とともに来談した。学習不振の背景にどんな要因が考えられるのかについて、多角的に論じなさい。(学習院大学大学院 2013年)⇒この問題についての解説をこちらに載せています⇒学習不振児 / 勉強ができない子供の本当の理由【事例問題】|臨床心理士指定大学院入試対策
例:心理療法で転移が大切であるとよく言われるが、どういう点で大切なのか多面的に考察しなさい。(神戸大学大学院 2013年)⇒この問題の解説をこちらに載せています⇒【過去問分析】精神分析ー転移とは|臨床心理士指定大学院入試対策
※序論、本論、結論にわけ、専門的知識を正確に論理的に書いていく。文字数の指示がある場合や、ない場合、いろいろあります。文字数については、この記事の下のほうに補足しています。
※【参考】論述対策についての詳細はこちら⇒必見!これだけ知っておけばなんとか書ける【論述対策】|臨床心理士指定大学院受験
※事例問題の論述対策についてはこちらです。⇒【論述対策】事例問題を斬る!何故事例問題は難しいのか?|臨床心理士指定大学院入試対策
穴埋め・正誤問題
例:エリクソンは、青年期の発達課題における危機を( )であるとした。青年期は、理想と思える人物や他者の考えに同一化しながら、役割実験や( )を繰り返し、自分にぴったりした生き方を模索する。(神奈川大学大学院 2024年度)
例:自己・他者の行動の背景にある心理(考え・感情・欲求・願望・信念)を理解する力のことを、フォナギー(Fonagy,P.)は、( )と呼び、境界性パーソナリティ障害の治療の文脈で論じた。(目白大学大学院 2025年度)
例:適応障害(DSM-5) に関する以下の記述の中で、誤っているものを1つ選べ。
1. はっきりとしたストレス因が確認できる。
2. ストレス因に相応な苦痛が出現する場合、適応障害と診断される。
3. ストレス因やその結果が終了すれば、症状は6ヶ月以上持続することはない。
4. 社会的、職業的、または他の重要な領域における機能の重大な障害が生じる。
5. 落ち込み、涙もろさ、絶望感、神経質などの抑うつや不安を伴う場合がある。
(国際福祉大学大学院 2024年度)
※穴埋め問題・正誤問題は、基礎さえ勉強し、過去問もやっていれば、さほど難しくない。用語説明や論述に力を注いでやりさえすれば、穴埋め問題は自然にできてくると思います。
時間配分
試験時間や出題数は大学院によって、本当に様々です。時間配分を間違えると、できる問題もできないことになってしまうため、トータル試験時間はどのくらいなのか?その中で何題でるのか?は重要なのでチェック必須です!実際に家で時間を測って練習することがおすすめです。
例)
- 論述問題3題(字数指定なし)+用語説明7題 =試験時間2時間
- 論述問題3題(字数指定600字以内)+用語説明10題=試験時間1時間半
- 論述問題2題(3題中2題選択で字数指定なし)+用語説明5題=試験時間1時間
解答用紙の形式
解答用紙も様々なタイプがあります。過去問をチェックするときに、問題だけでなく、解答用紙がどのタイプか?もチェックしておきましょう。。
タイプ1 白紙タイプ
問題が書いてあって、その下は線もマス目も何もない白紙の状態。

タイプ2 罫線タイプ
罫線がだ~っとひいてある。

タイプ3 原稿用紙タイプ
マス目がある。

字数指定
タイプ1 文字制限なし
「◎◎◎◎ついて述べなさい」だけで文字数について指示がない場合。
400字は最低でも書いたほうがよい(と思います)。文字数は、少ないより、多いほうがいいと思いますが、長すぎて、何を書いているのかポイントがわからないような文であれば、400字~600字程度に留めて、ポイントがまとまっている方がよい。
タイプ2 ●●字以内
「以内」は8割~10割
例えば、「600字以内」であれば、601字ならダメ。
タイプ3 ●●字程度
「程度」は、プラスマイナス1割
例えば、「600字程度」であれば、601字はOK。
200字、400字、600字、などと言ってもピン!とこないと思いますが、何度も練習するうちに字数の感覚がわかるようになります。何度も書いて書いて、練習しましょう。
過去問チェックは早めにすべし!
以上、ほとんどの大学院で出題する共通の形態について、書いてきました。
しかし、大学院の試験は、個々の大学院で個性がそれぞれ違うので必ず過去問をチェックしてください。用語説明や論述といった「形」は同じでも、「内容や範囲」は大学院ごとに個性があります。(例えば、統計が出る出ない、事例問題が出る出ない 発達臨床に関する問題が出る出ないなど)
過去問なんて難しくて…..何を書いていいかわからないし、解けないよ~と泣きたくなってくるかもしれません。が、できなくてもよいのです。
過去問チェックの目的は解けることではなく、どんな問題が出るの?を掴むのがこと。出題しない分野をやみくもに勉強してても、無駄になってしまいます。ゴールはここなんだ!ということがしっかり見えた上で効率的に勉強にとりかかるためです。早めにチェックすることを強くおすすめします。
実は、こんなことを言っている私は、実際、過去問を見るのが怖かったです。見て、わからない問題だったら、落ち込むし、焦るし、もうダメかも~と思ってしまうからです。それでも、本番前の2ヶ月くらい前にはチェックして、取り組み始めました。やっているうちに、あれもしておかなきゃ、これもしておかなきゃ、足りない勉強がいっぱい出てきてしまい、「もっと早くから見ておけばよかった(泣)」と思いました。
まとめ
筆記試験の専門科目
- 試験の内容は、【臨床心理学】が中心、プラス 【基礎心理学】の基礎知識
- 形は、【用語説明】【論述問題】【穴埋め問題】
- 【試験時間】【出題数】【字数指定】【解答用紙タイプ】も、重要。
- 何度も練習し、時間感覚、字数感覚を養う。
- 過去問は早めにチェックし、志望校の個性をとらえた上で効率的に勉強にとりくむ。
おすすめ書籍
いかがでしたでしょうか?だいたいの試験問題はつかめたでしょうか?なにやら大変そうだと思うかもしれませんが、全く心理学のことを何もわからかった私でもやれたんです。また、ともに受験勉強をがんばってきた私の友人たちも、知識ゼロの状態から乗り越えていきました。これを読んでいるあなたも、きっとできるはず★
>>次のページは、
↓↓