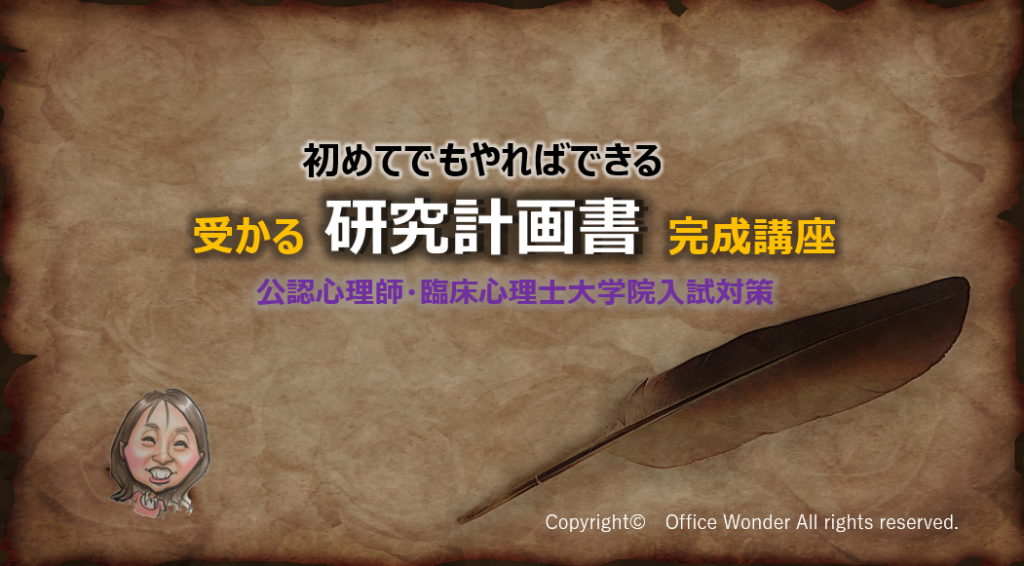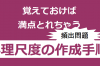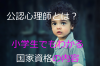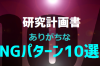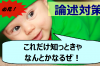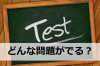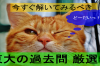ご訪問ありがとうございます。こんにゃろうです。
さて、今回は、心理職の資格についてです。
公認心理師法が、2017年9月に施行され、そして2018年9月に第一回公認心理師試験が実施され、2019年4月より、初の公認心理師が誕生しました。
それまでは、心理職としての資格は、民間資格の「臨床心理士」が最高峰といわれていたのですが、新たに国家資格としての「公認心理師」が誕生したのです。
さてさて、今回は、他学部出身者、特に社会人を長く経験したり、子育てに長く専念したり、人生の終盤になってから、心理職になりたいという人に向けての記事です。
「公認心理師をめざすべきか、臨床心理士のみをとるべきか、迷っています。」
というお問合せが多く寄せられています。
公認心理師よりも臨床心理士のほうが早く資格が取れる
他学部出身者が、「公認心理師」を得るためには
- 大学の心理学部に入り直し卒業(4年)→大学院を修了(2年)→修了後、資格試験を受けて合格すれば、翌年の4月から資格を名乗れる。(1年)
- 大学の心理学部に入り直し卒業(4年)→実務経験(2年以上)→資格試験を受けて合格すれば、翌年の4月から資格を名乗れる(1年)
というルートとなりいずれも、計7年~かかりますよね。
最近は、大学の学部編入という道も開かれており、
- 大学の心理学部に編入し卒業(2~3年)→大学院を修了(2年)→修了後、資格試験を受けて合格すれば、翌年の4月から資格を名乗れる。(1年)
※学部編入は、大学によって2年生から編入できる場合と、3年生から編入できる場合とあります。このルートの場合は、計5~6年かかります。
他学部から心理職を目指す人の中には、一度社会に出て、社会人になってから進路変更する方や、子育てをしながら目指す方、40代50代から目指される方も多いです。そんなときに、この5年~7年という時間の長さは、かなりのネックになりますよね。。。。
一方で「臨床心理士」は、公認心理師法に関係なく、今までどおり
- 臨床心理士指定大学院に入学し修了(2年)→修了後、資格試験を受けて合格すれば、翌年の4月から資格を名乗れる。(1年) 計3年です。
公認心理師(5年~7年)VS 臨床心理士(3年)であれば、、、
今から心理職をめざすためには、臨床心理士のほうが早く資格がとれるんだから、そっちのほうがいいじゃないか、ということになりますね。しかし、そんな単純にはいかない。
公認心理師と臨床心理士、どっちが価値が高いの?
しかし、公認心理師は、国家資格。臨床心理士は民間資格。
〇これからは公認心理師を目指したほうがよいのではないか?
〇いやいや、臨床心理士は、民間資格であったとしても、長年、専門性を担保してきた資格であるから、信用度は高いはず。臨床心理士があれば、これからも心理職に就けるのではないか。
〇いやいや、ダブル資格がよいのでは?
などと思いを巡らせて迷われているのではないかと思います。
「臨床心理士or公認心理師のどちらが有利か。どちらを取ったほうが良いのか」問題に、今回は、こんにゃろうの私見ですが、答えていきたいと思います。
まず、どちらの資格が価値があるかという問題に両者の考えを比較したいと思います。
臨床心理士推進派の考え
・臨床心理士は、大学院を修了していないとなれない。だから臨床心理士こそがプロフェッショナルだという考え。
・臨床心理士は歴史があり、専門性をこれまで地道に蓄積してきたという実績を強調する考え。
・「Gルート問題」にまつわる臨床心理士の優位性を強調する考え。
Gルートというのは、現任者の経過措置ルートで、Gルート問題というのは、純粋に心理の仕事だけをやってきたわけではないのだけど、現任者と認められて、資格試験を受けて公認心理師の資格がとれるという問題です。
(Gルートで公認心理師になった人は、隣接の領域の職業の方が多いです。、例えば、看護師、保健師、精神保健福祉士、言語聴覚士、教師などの臨床経験が5年以上で現任者と認められる)(※経過措置はすでに2022年度で終了しています)。
この臨床経験ていうのは、何をもって経験というのか難しく、ある程度は、人のこころの支援に関わってきた人ではあるものの、本当に専門性があるかという点では、疑問が残る部分があります。(もちろん専門性をしっかりもっている方もいます。)
それに対して、純粋に心理臨床を、深く追求し、訓練もしっかり受けている大学院を修了した臨床心理士は、公認心理師よりも高い専門性を有しているという考えです。
・公認心理師のカリュキュラムは穴だらけで、専門性が薄いという考えもある。
公認心理師推進派の考え
・臨床心理士は民間資格だけど、公認心理師は国家資格なので、就職には国家資格が有利という考え。
・医療機関では、令和4年度診療報酬改定において、公認心理師の業務が診療報酬に算定されるようになり、そのため、医療機関への就職は、公認心理師資格を持っている方が有利であるという考え。
・公認心理師の大学のカリュキュラムが、徐々に確立してきていて、中には、公認心理師だけを養成する大学もある。(臨床心理士だけを希望する人は受験できない。中高年や人生の終盤から心理職を目指す人(人生に時間があまりないですよね)にとって、こういった大学院が増えていく現象は、悲しいですね 😥 )
・これからは、「大学心理学部卒⇒大学院修了」で公認心理師のカリュキュラムを6年間受けて、その後、資格試験に合格して公認心理師を名乗る人が多く誕生する。そうなると名実ともに公認心理師が、最高峰の心理職になるという考え。
あらためて、両者の考えをみると、これから資格をとろうと考えている人にとって、ほんとにどっちの資格を取ったらいいのか迷いますよね。
求人情報はどうなっているの?
現在の心理職の求人を見る限り、臨床心理士も公認心理師もどちらかが、極端に求人が少ないということはありません。(2023年4月現在)
「臨床心理士、公認心理師のいずれか」となっている求人が一番多いです。
例
〇某市 スクールカウンセラー
- 以下いずれか。
- 臨床心理士、公認心理師、大学院修了後臨床経験を1年
〇某メンタルクリニック
- 臨床心理士、公認心理師 いずれか
〇某自治体、発達支援専門員
- 臨床心理士・臨床発達心理士・公認心理師のいずれか。
ただ、中には、
「公認心理師」に限っているところもありますし、
「公認心理師および臨床心理士の資格を有する者」とダブル資格を条件にしているところも、目にします。
しかし、一部にそういった求人先があるというだけで、
- 臨床心理士よりも公認心理師のほうが有利だ!
- ダブル資格でないと就職できない!公認心理師資格だけ(or臨床心理士資格だけ)ではだめだ。
と決めつけてしまうのはどうかなと思います。
就職には採用側の考え方も大きく影響する
ここで注意してほしいのは、就職には採用側の考え方も大きく影響するということも忘れないでください。
採用側は、
・資格を重視しているのか。
このパターンは、医療機関など、診療報酬の関係上(?)公認心理師に限定している場合が多いのではないかな)
・その人が受けてきた教育歴を重視しているのか。
(応募条件は、資格どちらかになっているけれど、個々の教育歴を重視するもの)
例えば、他職種からGルートで公認心理師になった人は、カウンセリングなど心理臨床の専門性を強く求められる職場では、大学院で訓練を受けていないため採用されない可能性が高いということもよく聞きます。
大学院修了した公認心理師なのか、大学院修了していない公認心理師なのかといったところがみられるのではないかということです。
→このパターンだと臨床心理士資格のみを持っている人には希望が持てますよね。
・資格はどっちでもよいけれど、その人の専門性や人間性を重視する場合。
←これまでの職歴を重視する。応募するときに作文を提出させ、その内容や面接を重視する。
などいろいろあると思います。そうすると、人間性や専門性を重視するようなところは、資格どっちよりも、個人の人間性や専門性で勝負することも可能ですよね。
※いずれにしろ、求められる業務によっても、求められる資格要件も違ってきます。やりたい領域が決まっているのであれば、就職したい先の資格条件をあらかじめ調べてみるとよいですね。
※資格をとった直後は、心理士1年生で専門性があまりないと思うかもしれませんが、大学や大学院を出ている、資格試験を合格している、というのは、それ自体で専門性があると認められるので自信をもってください。
※最初は、思うところに就職できなくても、やりたい領域の隣接領域で就職して、経験年数を蓄積した上で、徐々にやりたい領域へとチャレンジしていくといった、レベルアップを長期的に考えていくという道もあります。
これからも、臨床心理士資格だけで十分心理職として活躍できると予想。
以上、公認心理師VS臨床心理士について、考えるところを書いてきました。なるべく中立の立場で書いたつもりです。
ここからは、私の個人的な予想ですが、臨床心理士資格はなくならないと思います。
臨床心理士という資格は、長年、その専門性を培ってきたという歴史があります。
臨床心理士は民間資格ではあるものの、臨床の知を積み重ね、国公立の小中学校のスクールカウンセラーになるためには必須とされる資格になるまで成長しました。臨床心理士の認知度、社会的信用度は十分にあります。
個々の職場の求める人物像にもよりますが、心理臨床の専門性が強く要求される場では、
臨床心理士資格オンリーでも必要とされ、その活躍は期待されていると思います。
まとめ
「公認心理師、臨床心理士どちらをとったらよいでしょうか?」へのこんにゃろうの答え。
ダブル資格をとれそうならそれに越したことはないけれど、
- 自分の年齢
- 経済的、時間的余裕
- 資格をとって何をやりたいか。
を総合的に考えて決めよう。
これを読んでいるあなたが、公認心理師をとるには時間かかるし、時間的余裕を考えて無理そうなら、臨床心理士だけとってはやく心理の仕事をしよう。
一方で、公認心理師のカリュキュラムしかない大学を検討していて、卒業、修了しても臨床心理士がとれないことで悩んでいる人もいるかと思います。
いずれにしろ
どっちかの資格しか取れないような個人的状況があれば、片方だけでもよいのではないかな。
片方だけの資格だからといって、自分を卑下することはないし、自分の人間性や専門性(←これは研鑽するよう努力が必要)を磨くことが重要。
片方だけの資格で、応募できない求人は潔くあきらめよう。
自分の中で、何が一番大切なのかを考えつつ、現実的な問題と折り合いをつけながら、生きていくことが大切かなと思います。
資格云々の話だけでなく人生には、折り合いが大切な時は多々ありますね。
また、資格云々よりも、本当の意味で社会に貢献できる人材になることをめざすことが一番重要ではないかと思います。
以上、ここまでお読みくださりありがとうございます。色々書きましたが、あくまで私の個人的な考えであるということにご留意ください。
進路を決める際の参考になれば幸いです。
今回は「臨床心理士と公認心理師」資格取得のみの内容となりましたが、もちろん、これ以外の選択肢も人生にはあるということを補足として加えておきます。